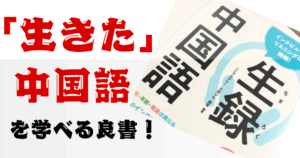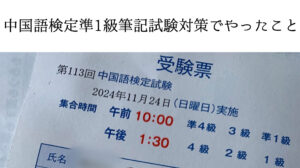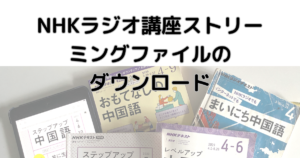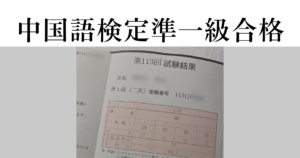「さようなら」の時に“再见”ばかり言っていては芸が無い
今回は初学者向けで2、3分程度で読み終えてしまえる内容となっています。
中国語のさようならの言い方として我々中国語学習者が真っ先に思い浮かぶのは“再见”でしょう。
ただ、中国人の話している様子を見ていると“再见”ってほとんど使っていないことに気づきます。
我々日本人でも「さようなら」は滅多に使わないのと同様ですね。せいぜい小中学生が先生に対して下校前の挨拶として使うくらいでしょうか。
中国人からすると“再见”はすこし硬い表現で、教科書的で場合によっては冷たく感じるんだそうです。
そんなわけで中国人に対してあんまり“再见”ばっかり使っていると距離も縮められません。
本投稿では私が知り合いの中国人に聞いた話やYoutubeで学んだ内容のメモなどをもとに“再见”以外の中国語の「さようなら」を、使用頻度の高いものに絞り込んでサクッと紹介いたします。
中国語での「さようなら」の言い方 種
“再见”が使われているシチュエーション

日本の「さようなら」と同じく、中国語で“再见”を使うシーンとしては、親が低学年以下の子供たちに、“跟小朋友们说再见吧。”(みんなにさよならしましょーね)
といったときが多いようです。
“跟小朋友们说再见吧。”(gēn xiǎo péng yǒu men shuō zài jiàn ba)
あとは例えば、友達が引っ越しなどでこの先しばらくの期間会えなくなりそうな別れのシーンなど、割とさようならが重い意味を持つときにも“再见”を使うそうです。
いずれにせよ、単独で“再见”のみを使うとカタくて距離感がある印象を与えてしまいます。
例えば友達とけんかをしてバシーンとドアを閉め“再・见!”などの使い方もよくあるみたいです。
そのため文末に”罗”を加えて“再见罗~!”と言ったり、“再见再见。”と繰り返し言ったり、“那我们再见,拜拜。”のように他の言葉と一緒に使ってフレンドリーな言い方にしています。
中国人が友達同士で最もよく使うさようならのフレーズ“拜拜”

中国人が友達同士で最もよく使うさようならのフレーズは
“拜拜。”「バイバーイ」
です。
これ、中国人の発音のややこしいところが普通にピンイン通りに発音すれば、(bài bài)なんですが、2声っぼく(báibái)って発音しているんですよね。
なので英語のバイバイとなんかちがうように聞こえるのです。中国人っぽく言いたいなら2声2声で発音しましょう(笑)
ただ、この2声2声はこどもっぽい可愛さの響きになるようなのでオッサンはあまり2声の発音を強調しすぎないほうがいいかもしれません。
2声の発音に合わせて若い人はチャットで“白白。”と使ったりもします。
“拜拜咯。”として末尾に“咯”もっとカジュアルでフレンドリーな響きになります。
また比較的若い人の間ではテキストチャットで”88“と送ってもバイバイの意味となります。
時折“掰掰。”(bāibāi)の漢字を使っているのも見かけますが、私の知っている何人かの中国人に聞いてみたら皆“掰掰。”は使わないなぁ、という回答でした。
グループで遊んだ時などによく使う「じゃあねぇ~」にあたる“我先走了”“走啦”

“我先走了。”(wǒ xiān zǒu le)「じゃ、先にいくね~」
も友達同士でよく使う「さよなら」です。特にグループで集まったり遊んでいる時で帰り際にこのフレーズは使っています。
短縮してもっと簡単に
“(那,我)走啦。”(zǒu la)「じゃ、いくね~」
こちらも“我先走了。”と同じシチュエーションで使えます。
フレーズを前に加えて我先走了を付け加えるともっと自然です。
“大家玩儿得开心,我先走了。”(dà jiā waér de kāi xīn wǒ xiān zǒu le)「じゃみんな楽しんでってね、先にいくね~。」
「またね!」にあたる“回头见。”/“下次见。”/“改天见。”

またね!は
“回头见。”(huí tóu jiàn)/“下次见。”(xià cì jiàn)/“改天见。”(gǎi tiān jiàn)/“待会见。”(dài huì jiàn)
回头は字を見ると頭を回すという事で、「振り返る、振り向く」という意味もありますが、ここでは「しばらくして.あとで.後ほど」という意味です。省略して“回见。”というときもあります。
待会は待一会儿(しばらくして.少し待って.)の短い形。
”回头~“や”~见“はいろいろな単語と組み合わせて使える便利な言い方です。
皆さんのなかには中国語のオンラインレッスンを受講していらっしゃるかたも多いことでしょう。
レッスンの終わりに先生に「また次のレッスンで!(会いましょう)」という意味で、
(那,我们)下节课再见。/下节课见。
なんて言い方もできます。
これは中国語を勉強し始めたときに、いの一番に習う“明天见。”(明日会いましょう)“下周见”(来週会いましょう)と同じ使い方ですね。
また见を聊や聚などの別の動詞に置き換えて
”下次聊。“/”改天聊。"/"回头聊。"「また話そうね~」
"下次聚。"/"改天聚。"/"回头聚。"「また集まろうね~」
似たようなフレーズで
“下次再聊吧。”(xià cì zài liáo ba)「また今度話そうね」
もあります。これは先程の下次聊などと同じ意味で使われるときもありますし、話の流れでは「(その話はとりあえずもういいから)また今度にしようぜ」などという意味合いになることもあります。
割とフォーマルな言い回し

正式な場面や礼儀正しさが求められるシチュエーションでは
“先告辞了。”(xiān gào cí le)「お先に失礼いたします」
“失陪了。”(shī péi le)「失礼いたします」
“再联系。”(zài lián xì)「また連絡します」
“再见,保持联络。”(bǎo chí lián luò)「連絡を取り合いましょう」
”你先忙。“(nǐ xiān máng)「お先に用事をどうぞ→どうぞどうぞ、こちらの事はお構いなく、の意味合い)」
”保重。“(bǎo zhòng)「お元気で/お大事に」(ビジネスシーンに限らず英語の”Take good care.”のように友達にも使う)
など。上司や顧客への拝辞のフレーズとなります。
先ほど紹介した”回头“と組み合わせて”回头再联系。“(また後で連絡します。)なんて言い方もあります。
(”我回头再联系你。“を省略した形です)
グループチャットから抜ける時などに使うユーモアな「さようなら」
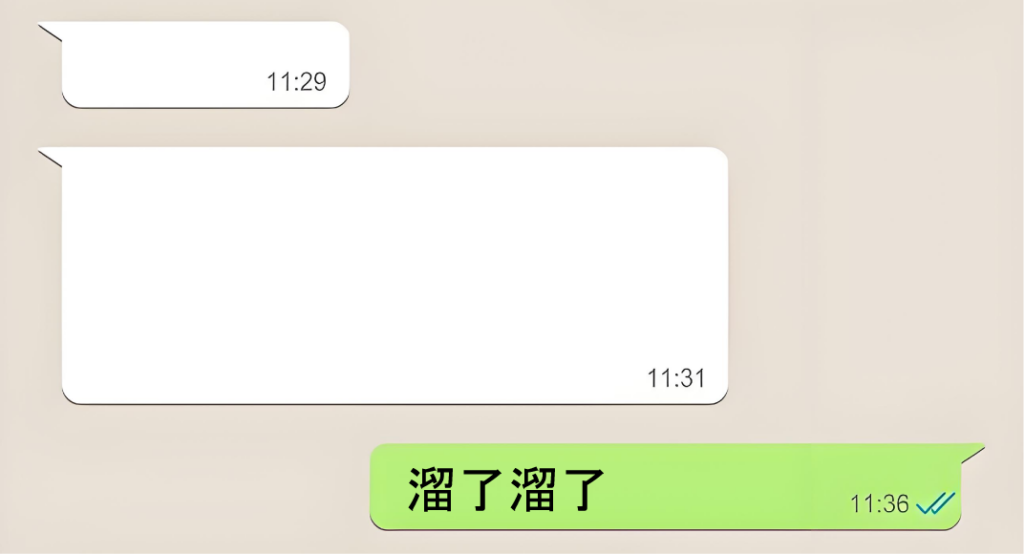
割とカジュアルで可愛らしく、もしくはちょっとおちゃらけた感じでの「さようなら」の言い方であったり、オンラインのグループチャットのやり取りから抜けるときのフレーズでは
”溜了溜了。“(liū le liū le)「じゃあ抜けるわー/撤収撤収~」
”先撤了。“(xiān chè le)「撤収~」
などがあります。
チャットを終了したり抜け出す時以外にもサムいこと言ってしまって気まずくしてしまったり、ヤバいことが発覚してしまった時にも使います。
たまにテレビの昭和時代のバラエティ番組の紹介で、コメディアンの植木等のお決まりのネタで、しょーもないことを言った後に「お呼びでない? こりゃまた失礼しました」と言ってはけていくシーンがありますが、”溜了溜了。“は使い方によってはその感覚に近いとも言えます。
あ、ちょっとネタが古すぎましたね(汗)
以下はHiNativeでネイティブが紹介していたチャットの会話例です。「撤収撤収~」的な意味合いで使っている例です。
A: 我姐说昨天中午在一家自助餐厅看见你大吃大喝。你不是在减肥吗?所以我说她一定认错人了。
B: 溜了溜了。
A:姉が言ってたよ、昨日の昼にビュッフェレストランであなたがたくさん飲み食いしてるのを見かけたって。ダイエット中じゃなかったの?だから私は「絶対人違いだよ」って言っといたんだけどね。B:うわ~逃げよっ。
”溜了溜了。“は主にネット用語、ネットミーム(玩梗 wán gěng)として使われていて、いろいろな表情包などにも使われています。
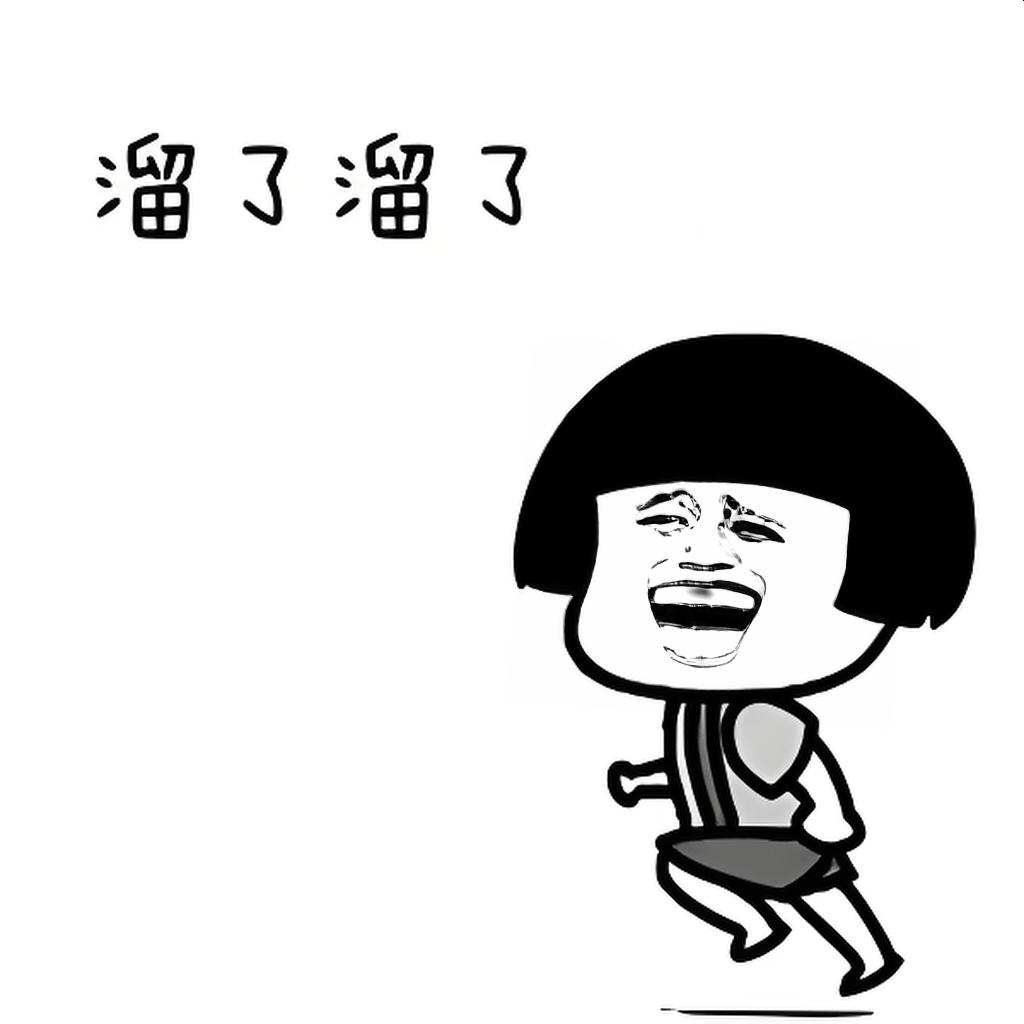
また普通にちょっとやる事が発生して抜けるね~、なんて言うときも
”忙起来了,溜了。“(máng qǐ lái le liū le)「ちょっと忙しいわ、またね」
という風に使えます。
ついでにですが、チャットから抜ける時のいい口実として使ういわば「常套手段」的フレーズでは
まとめ
日本語の「さようなら」にあたる中国語フレーズは他にも電話の会話を切り上げる時とか、シチュエーションを挙げだすときりがありませんのでこの記事では主に日常生活で使用頻度の高いフレーズに絞り込んで紹介いたしました。
当面はこの記事で紹介したフレーズだけでも自然と口から出てくるようにするのが良いでしょう。
その後に使用頻度の高くない特定のシチュエーションで使うフレーズ、例えば友人が遠くへ旅立つ時や遠方から来訪されたお客さんが帰るときにかけるお決まりフレーズの"(祝你)一路平安!"(Yīlù píngān)「道中ご無事で!」、"一路顺风!"(Yílù shùn fēng)「道中ご無事で」なんかもストックフレーズに加えていけばよいでしょう。
もしくはそういうフレーズがある、という事だけ頭に入れておいて、直前にちゃっかりスマホなんかで再確認するのでもよいのではないでしょうか?
使用頻度がそれほど高くないですし、使い方、使うべきシーンだけ覚えておけば後は肩ひじ張らずに具体的なフレーズは直前に“カンニング"でよいでしょう。いずれにせよ何回か使っているうちに自然に身に付いてきますし。
まずは実際に使ってみること、その繰り返しで挨拶フレーズは身に付いていきます。中国人の知り合いや友達にいろいろなパターンの「さようなら」を積極的に使ってみましょう。